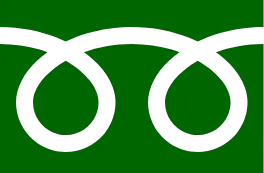終活はどのように人生の終わりを迎えたいのか考え、目標や計画を立てて死に向けて行動することです。
終活を行っておくと有事の際に家族へ迷惑をかけずに済みます。
しかし、事前にやることを調べずに行うと、大切な情報が抜けていて家族を困らせてしまうこともあるでしょう。
本記事では、終活でやることをリスト化したうえで、注意点や困ったときの相談先を紹介します。
終活を始めたいけど何からすればいいのか分からないという人は、参考にしてください。

記事監修者プロフィール
遺品整理士歴10年、これまでに5,000件以上の遺品整理や特殊清掃に携わる。手がけた遺品整理で発見された貴重品のうち、お返ししたタンス預金の合計だけでも3億3千万円にも上り、貴金属などの有価物を含むと5億円近くの金品を依頼者の手元に返して来た。
遺品を無駄にしないリユースにも特化。東南アジアへの貿易を自社にて行なっており、それに共感を覚える遺族も非常に多い。また不動産の処分も一括で請け負い、いわるゆ「負動産」を甦らせる取り組みにも尽力して来た。
一般社団法人ALL JAPANTRADING 理事
一般社団法人家財整理相談窓口会員
一般社団法人除染作業管理協会理事
宅地建物取引士(日本都市住宅販売株式会社代表取締役)
株式会社RISE プロアシスト東日本
代表 仲井
終活は何から始めるべきか?
「終活」を始めるにあたって、まず手をつけるべきとされるのが「自分の想いを整理し、言葉や形で残すこと」です。
具体的には、自分がどのような人生を歩んできたかを振り返り、これから先にどんな終え方を望むのかを考える作業が重要となります。
その第一歩として、多くの方は「エンディングノート」を作成することからスタートするのが一般的です。
エンディングノートは、財産の整理や葬儀の希望、医療や介護の方針、さらにはメッセージや伝えたい想いなどをまとめておくノートで、法的効力こそないものの、家族や大切な人に対して自身の考えを伝えやすくし、トラブルや混乱を防ぐための手立てとなります。
終活をスムーズに進めるには、「自分が何を大切にしたいのか」を明確にすることが不可欠です。
たとえば、自分の死後に誰に何を残したいか、どんな形で葬儀やお別れ会をしてほしいか、延命治療や臓器提供への意志はどうかなど、考えるべきことは多岐にわたります。
これらを一度にすべて決めるのは難しいため、まずはノートやパソコンに箇条書きで思いつくまま書き出してみるとよいでしょう。
書き出してみることで、自分の優先順位や気持ちの向きどころが見えてきます。
さらに、財産整理も重要なステップです。銀行口座や証券口座、保険などの資産や負債を洗い出し、それをどのように分配あるいは処分したいかを検討します。
資産状況が複雑な場合や相続について専門的な知識が必要な場合は、弁護士や税理士、司法書士などの専門家に相談するのも一つの方法です。
事前に自分の意思をはっきりさせておくことで、相続トラブルを未然に防ぐことができます。
また、家族が手続きを行う際の負担を軽減するためにも、口座や保険の契約先一覧などを整理しておくとスムーズです。
終活には、医療面での事前準備も含まれます。万が一、自分が意思表示できなくなったときにどの程度の治療や介護を望むかという「リビング・ウィル(事前医療指示書)」の作成や、延命措置の可否について家族と共有しておくことは大切です。
医師やケアマネージャー、家族とこまめにコミュニケーションを取り、自分の希望をしっかり伝えておくことで、周囲は安心してサポートにあたることができます。
終活で最も大切なのは、単に身辺整理だけでなく「安心感」を生むことです。
自分自身が納得し、家族や大切な人も混乱や負担なくサポートできる状態を整えておくことが、豊かな人生の終盤を迎えるうえで欠かせません。
エンディングノートの作成や財産整理、医療や介護に対する意向の確認など、やるべきことは多岐にわたりますが、少しずつでも手を動かし、言葉や情報をまとめておくことが、終活の第一歩として最も大切です。
事項にやるべき事リストをまとめましたので、参考にされてください。
終活でやることリスト10項目

終活は各々の目標が異なるため、どのような行動が必要なのかは人によって異なります。
しかし、下記の10項目は終活でよく実施されるため、事前知識として知っておいた方がいいでしょう。
- エンディングノートの作成
- 資産の確認
- 遺言書の作成
- 身辺整理
- 葬儀やお墓の準備
- 住まいの見直し
- 介護や終末医療の方針決定
- デジタル資産の整理
- 人間関係の見直し
- 余生の計画
それぞれの項目ごとに具体的にどのような行動をすればいいのか、詳しく解説していきます。
エンディングノートの作成
前項で詳しく解説していますが、エンディングノートとは、何かあったときに備えて自分の情報や要望を書き残しておくノートです。
エンディングノートはどのような内容を記載するのか決まりはなく、自由に記して問題はありません。
家族が困らないように口座の情報や加入サービスを記す人もいれば、家族に宛ててメッセージを残す人もいます。
もし、どのような内容を書くか迷ったら、市販のエンディングノートを購入して書くのがおすすめです。
市販のエンディングノートであれば、自身の死後に必要な情報が網羅されていて、家族もスムーズに手続きや葬儀の準備を進められるでしょう。
なお、エンディングノートには遺言書のような法的拘束力がありません。法的効力を求める場合は、必ず遺言書に記載してください。
資産の確認
エンディングノートの作成と並行して、資産の確認を行うことも大切です。
資産の確認では、まず自身がどのくらいの資産を保有しているかを確認します。そのうえで、必要な老後資金の算出や相続の分配、相続税対策などを考えましょう。
また、相続の手続きがスムーズに進むように、財産目録(資産の一覧表)も作成してください。財産目録に記載する内容は、下記の項目が挙げられます。
- 銀行口座
- ローンや借金
- 有価証券(株や手形など)
- 不動産
- 貴金属
- 加入している生命保険
- 仮想通貨などのデジタル資産
特にデジタル通貨は相続のときに見落とされてしまうことが多いので、家族が分かるように必ず残しておきましょう。
遺言書の作成
資産の確認が終わったら遺言書の作成を行うといいでしょう。
遺言書は被相続人(亡くなった人)の意思を記した書類です。
エンディングノートと違って法的効力がある代わりに、決まった形式で作成しなければなりません。
遺言書は主に下記の3つの種類があります。
|
種類 |
内容 |
|
公正証書遺言 |
遺言者の口述を元に公証人が作成する。証人が2人必要なうえに手間や時間がかかるが、無効になりにくい。 |
|
自筆証書遺言 |
遺言者が自ら書く。手軽に作成できて費用がかからないが、形式通りに書けておらず無効になることも多い。 |
|
秘密証書遺言 |
遺言者が自ら作成し、内容を秘密にしたまま公証役場で認証してもらう。自筆証書遺言と同様に、形式通りに書けてなくて無効になることも多い。 |
このなかでもおすすめなのは公正証書遺言です。手間や時間はかかってしまいますが、無効になりにくいメリットは大きいでしょう。
また、遺言書を作成する場合は、専門知識が必要になることも多いので、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
身辺整理
ほかの項目と並行して、遺品整理の負担を軽減させるためにも身辺整理を始めましょう。
遺品整理は手間や費用がかかるため、亡くなった後の作業のなかでも一番負担がかかります。
生前のうちに物の量を減らして、できるだけ遺品整理の負担を減らすことが大切です。
もし、どうしても残しておくものがあれば、死後はどのように処分するのかエンディングノートに記載しておくといいでしょう。
処分方法まで記載しておけば、遺品整理の時に家族が困りません。
なお、身辺整理は時間がかかるうえ、肉体労働もともなうこともあるため、元気なうちに始めるのがおすすめです。
葬儀やお墓の準備
生前のうちに葬儀やお墓の準備を進めておくと、家族の負担を軽減できます。
葬儀は限られた時間のなかで寺の手配や遺影の準備などを進めなければなりません。
同様にお墓も先祖代々のお墓に入るのか、別の方法を検討するのか家族間で話し合う必要があります。
これらの手配や話し合いも家族に負担をかけるため、事前に準備しておきましょう。
葬儀については葬儀社に生前相談をして、どのような葬儀にしたいのか決めておくことがおすすめです。合わせて、葬儀へ参列してほしい人のリストを作成して、連絡先も残しておきましょう。
お墓については事前に先祖代々のお墓に入るのか、新しいお墓を購入するのか、樹木葬や散骨などの墓に入らない供養方法にするのか決めておくのをおすすめします。
ただし、葬儀は家族と親族・友人間の人間関係に影響し、お墓は家族が管理していかなければなりません。
独断で決めてしまうと、かえって家族に明確をかけてしまうことがあるため、家族とよく相談して準備してください。
住まいの見直し
老後を見据えて、今の住宅に住み続けるかも考えなければなりません。
歳を取ると思うように体が動かなくなって家の中で転倒してケガをするおそれがあります。
連れ合いがいたり子どもと同居したりしていれば安心ですが、ひとりだけだと最悪の場合、孤独死につながることもあるでしょう。
住まいの見直しをする際は、主に下記の選択肢に迫られます。
- 居住している住居をバリアフリーリフォームする
- 子どもと同居する
- 高齢者向け住宅または施設に引っ越す
いずれの選択肢も自分だけでなく家族にも大きな影響を及ぼすため、ひとりで決めるのではなく家族とよく話し合って決めるようにしましょう。
介護や医療の方針決定
歳を取るにつれて介助が必要になったり病気を患ったりする可能性も考えられるため、介護や医療の方針を明確にしておきましょう。
介護の方針は下記の事項を決めておくことをおすすめします。
- 介護の種類(自宅介護・訪問介護)
- 介護をお願いする人
- 介護費用の負担元(年金・預貯金)
介護の方針を明確にしたら、それに合わせて施設を見学したり介護サービスを検討したりして、必要な費用も算出して準備しておいてください。
医療の方針では延命治療や臓器提供の希望を明確にして家族に伝えておきましょう。
合わせて、かかりつけの医者や常用薬も分かるようにしておいて、急な入院時でも対応できるように準備しておいてください。
デジタル品の整理
終活で見落とされがちなのが、デジタル品の整理です。
近年、デジタル化が進んで写真や文章などがデータで保存されていることが増えています。また、仮想通貨や電子マネーなどのデジタル資産も増えており、遺品整理や遺産分割のときにトラブルになるケースも多いです。
トラブルを避けるためにも、終活のときにデジタル品も整理しておきましょう。
デジタル品の整理方法は、不要なデータは削除して、残しておくデータは死後の処分方法を明確にしておくのがおすすめです。
デジタル資産は財産目録を作成したときに一緒に記載して、サイトやアプリへログインが必要ならIDやパスワードも必ず記載しましょう。
また、遺品整理のときにスマートフォンやパソコンの中身を確認することもあります。ロック解除のパスワードも忘れずに書き残しておきましょう。
人間関係の見直し
より良い余生を過ごすためにも、人間関係を見直すこともおすすめです。
大人になると仕事や育児に忙しくて人間関係が疎遠になってしまうこともあるでしょう。また、反対に我慢して付き合い続けている人間関係もあるかもしれません。
会いたい人に連絡を取らなかったり、ストレスがたまるような付き合いを続けたりしていると、自身の死を見据えたときに後悔してしまうこともあります。
気持ちよく余生を過ごすためにも、人間関係を見直してより良い余生を過ごせるように準備しましょう。
また、人間関係を見直した際に、何かあったときに家族から連絡してもらえるように、連絡してほしい人のリストを作成しておくのもおすすめです。
余生の計画
自分の死後に家族が困らないように準備を進めることも重要ですが、何よりも大切なのはどのように余生を過ごすかです。
高齢者になると時間に余裕ができたり体が衰えて身動きできなくなったりするためか、「あれをやっておけばよかった」と後悔することもあります。
人生の最期の時に後悔しないためにも、余生の計画を立てて目標に向けて行動することが大切です。
具体的には、やりたいことをリストアップして実行していくといいでしょう。
もし、何も思いつかなければ、新しいことに挑戦してみたり習い事を始めてみたりして、やりたいことを探してみるのもおすすめです。
より良い余生を過ごすためにも自身へ何がしたいのか問い続けて、思いついたものにはどんどん挑戦していきましょう。
終活のするときの注意点

終活は実際に進めていくうえで、いくつかの注意点があります。主に下記の3点には注意して行ってください。
- ルールに縛られない
- 終活の情報は家族と共有する
- 常に情報を見直して最新化する
なぜ、この3点に注意しなければならないのか、詳しい内容を解説していきます。
ルールに縛られない
終活はルールに縛られるとかえって本質を見失ってしまうため、あくまでも自分に合わせた方法で行うことが大切です。
終活で行うリストを解説しましたが、厳密にいうと終活にはルールがありません。無理にリストを守ろうとすると、かえって後悔してしまうこともあるでしょう。
例えば、現在、人間関係が充実しているのであれば、無理に人間関係を見直す必要はありません。それなのに無理に見直すと、大切な人と縁を切ってしまったりストレスを抱える人間関係を構築してしまったりするおそれがあります。
終活で行うリストは、自分にとってどの項目が必要かをよく考えて行動することが大切です。
終活の情報は家族と共有する
終活の情報は残される家族にも大きく関係があるため、必ず共有しておくことが大切です。
終活では前もって葬儀やお墓の準備を進めたり、死後の要望をまとめたエンディングノートや遺言書を作成したりします。
前もって準備していたことを家族に伝えておかないと、家族が気付かずに手続きや遺品整理を進めてしまうことがあるでしょう。
また、終活の情報を共有するだけでなく、相談することも大切です。
終活で決めた事柄のなかには、その後の家族と親族の付き合いに影響を及ぼすものもあります。
もちろん、自身の要望を尊重することは大切ですが、家族に迷惑をかけるのも本望ではないでしょう。
トラブルを避けるためにも、終活は家族と相談しながら進めてください。
常に情報を見直して最新化する
終活でまとめた情報のなかには変化を伴うものもあるため、情報を見直して最新化するようにしてください。
終活のやることリストのなかには、情報が変化したり意向が変わったりするものもあります。
特に資産やデジタル品は生活に密着しているため、常に変動があるでしょう。
終活でまとめた情報と実際の事柄が食い違わないためにも、最新化しておくことが大切です。
一か月に1回ぐらい見直す日を設けて、情報は最新のものか、目標に向けて行動できているかなど、確認するようにしてください。
終活は何歳から始めるべき?
終活を始めるタイミングは特に決まっていませんが、早ければ早いほどいいといわれています。
終活は身辺整理など肉体的に負担がかかるものもあれば、人間関係の整理など精神的に負担がかかるものもあります。
若い頃に始めれば体力や気力があるので乗り切れることも多いですが、歳を取ると億劫になってしまうこともあるでしょう。
参考:20代で終活する人が増えている理由と注意点について解説
一般的に終活は定年を迎えた60代から意識することが多いですが、最近では20代から始める人もいます。
一般的なタイミングに捕らわれず、元気なうちから始めるようにしてください。
参考:こんな方にこそ生前整理が必要!?生前整理はいつから始める?
終活で困ったときの相談先
終活を進めていると相続や老後の資金計画、葬儀などあらゆる分野で悩み事が生じるでしょう。
もし、終活で悩み事がでてきたら、下記の表を参考にして各窓口に相談してください。
|
相談事項 |
相談先 |
|
終活全般に関するサポート |
自治体、終活セミナーまたは終活のイベント、民間の終活アドバイザーまたは終活カウンセラー、遺品整理業者 |
|
家具や荷物などの生前整理 |
遺品整理業者、生前整理業者、 |
|
老後の資金計画について |
ファイナンシャルプランナー、銀行窓口 |
|
葬儀やお墓の悩み |
葬儀社、霊園、寺院(宗派によって神社、教会など) |
|
介護についての悩み |
高齢者支援センターなどの自治体、医療機関、 |
|
相続や遺言書についての悩み |
弁護士、税理士、司法書士 |
まとめ
本記事では終活でやることをリスト化して、10項目を解説しました。
しかし、先述したように、終活には決まった方法で行うというルールはありません。
リストに縛られず、自分が立てた終活の計画や目標に合う項目を実行していきましょう。
また、終活は残される家族に影響することが多く、独断で決めてしまうと死後に家族へ迷惑をかけてしまうことがあります。
トラブルへ発展させないように、終活は家族と相談したり情報を共有したりすることが大切です。