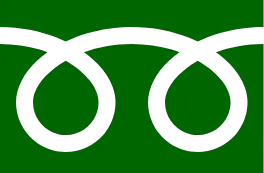現代社会において、私たちの生活にはスマートフォンやパソコン、インターネットサービスが深く根ざしており、多くのデジタル資産が蓄積されています。
これらのデジタル情報を適切に整理し、万が一の際に家族が困らないよう準備することが「デジタル終活」です。
本記事では、デジタル終活の重要性から具体的な実践方法まで、包括的に解説します。
デジタル終活とは?その重要性と現代社会における必要性
デジタル終活の定義と「デジタル遺品」「デジタル遺産」
デジタル終活とは、デジタル遺品に対する死後の取り扱いについて考える活動を指します。
これは、スマートフォンやパソコン、インターネット上に保管されているデータなどを、生前に整理整頓しておくことです。
デジタル遺品とは、パソコンやスマートフォンなどのデジタル機器内に保存されたデータ、およびインターネット上にあるデータ全般を指します。
具体的には、写真や動画、連絡先、メール、SNSアカウント、アプリやインターネットサービスのログイン情報などが含まれます。
これらには金銭的な価値が直接的にはないものも含まれますが、故人の個人的な情報や思い出が詰まっています。
一方、デジタル遺産とは、デジタル遺品のうち、特に金銭的な価値が高いものを指します。
ネット銀行やネット証券の口座、仮想通貨(ビットコインなど)、電子マネーの残高、デジタル著作物などが該当し、これらは相続の対象となります。
なぜ今、デジタル終活が注目されているのか?
現代社会では、インターネットやスマートフォンの普及により、私たちの生活はデジタル空間に深く根ざしています。
パスワードの管理が難しく、同じパスワードを使い回すことが厳禁とされる中で、パスワード管理の重要性が増しています。
デジタルデータは目に見えないため、使っている本人しか把握できません。
そのため、本人が亡くなった後、残された家族がSNSや有料サブスクサービス、証券会社のログイン情報などが分からず困ってしまうケースが多発しています。
放置されたデジタルデータは、第三者による不正アクセスや情報漏洩、なりすまし、金融犯罪につながるリスクがあり、さらに相続トラブルに発展する可能性もあります。
こうしたリスクを回避するために、生前のデジタル終活が非常に重要視されています。
普通の終活との違いとすべての世代に必要な理由
従来の「終活」が不動産や現金、預貯金といった「目に見える財産」の整理を中心とするのに対し、デジタル終活は「物」ではなく、目に見えない「情報」の整理に特化した活動です。
「終活」と聞くと高齢者が行うものと思われがちですが、デジタルデータについてノートに書き出す作業は、年齢に関係なく、スマホを買ってGoogleやSNSなどのアカウントを作ったときから始めましょうと専門家は推奨しています。
事故や病気、災害など、突然の事態は年齢を問わず誰にでも起こり得るため、若年層や働き盛りの世代を含め、すべての世代にデジタル終活が必要とされています。
デジタル終活を始めるメリット
デジタル終活は、自分自身と残された家族の双方にとって、大きなメリットをもたらします。
相続トラブルの回避と経済的損失の防止
デジタル終活を行うことで、遺産の相続漏れを防ぐことができます。
特にネット銀行やネット証券の口座など、通帳が発行されない金融資産は、その存在が家族に発見されにくい財産の一つです。
これらを整理しておくことで、相続税申告漏れによるペナルティや、遺産分割協議のやり直しといった問題を回避できます。
また、故人が契約していたサブスクリプションサービスが解約されずに利用料金が発生し続けたり、株やFXなどの金融資産が放置され価値が下落したりするといった相続人の経済的な損失も回避できます。
プライバシーの保護と個人情報の悪用防止
パソコンやスマートフォンに残っている写真や動画には、他人に見られたくない個人的な情報が含まれていることがあります。
デジタル終活により、見られたくないデジタル遺品を生前に処分しておくことが可能になります。
不要なサイトやSNSアカウントを削除するだけでも、プライバシーを守る上で効果的です。
さらに、インターネット上に個人情報を放置しておくと、最悪の場合、詐欺集団などに悪用されるおそれがあります。
SNSアカウントの乗っ取りなどの悪用事例も報告されており、デジタル終活はこうした個人情報の悪用・流出を防ぐ上で非常に重要です。
大切な思い出や情報の確実な継承
デジタル終活は、家族の思い出となる写真やビデオ、連絡先などをハードディスクにまとめるなど、長期間の保存に耐えられる形にして遺族に引き継ぐことを可能にします。
これにより、故人の思い出を振り返る材料として活用できるだけでなく、葬儀や法事などの際の連絡にも役立ちます。
また、スマートフォンが故障して買い替えるような日常的なアクシデントの際にも、IDとパスワードを記録していればすぐに見返すことができ、大変助けになります。
故人の意向を最大限尊重し、残された家族の負担を大きく減らすことができる点が最大のメリットです。
デジタル終活の具体的な進め方
デジタル終活は、目に見えにくいデジタル資産を扱うため、計画的に進めることが大切です。以下のステップに沿って取り組みましょう。
ステップ1:所有するデジタル遺品・資産の洗い出し(棚卸し)
まずは、ご自身がどのようなデジタル遺品を保有しているかを把握することから始めます。普段利用しているすべてのデジタルサービスやデバイスをリストアップしましょう。
写真や動画ファイルについては、パソコン、スマートフォン、タブレット、クラウドストレージ(Google Drive、iCloud、Dropboxなど)、USBメモリ、外付けHDDなどをチェックします。連絡先やメールデータは、スマートフォンの電話帳アプリや、パソコン・タブレットに標準搭載されているメールの受信フォルダ、Gmailなどのクラウド型メールサービスの受信フォルダを確認します。
アカウント情報の洗い出しには、ブックマーク、インターネットの閲覧履歴、クレジットカードの引き落とし明細、アプリのインストール一覧などを見返すと、漏れなく洗い出すことができます。
金融関連では、ネットバンキング、ネット証券口座、仮想通貨取引所・ウォレット、キャッシュレス決済アカウント、ポイント・マイレージなども忘れずに確認しましょう。
ステップ2:デジタル遺品の仕分けと整理(残すもの・処分するもの)
洗い出したデジタル遺品を、「残すもの」と「処分(解約)するもの」に仕分けます。
判断基準として、写真や動画は「死後に家族に見てほしいか、見られたくないか」、メールデータは「金融機関からのメールなど重要であるか否か」、アカウント情報は「利用頻度が高いか低いか」などで判断します。
個人的な記録や見られたくない情報は処分を検討しましょう。
保管方法については、残しておきたいデータは専用のフォルダを作成し、分かりやすい名前を付けてまとめておくと、家族も扱いやすくなります。
見られたくないデータがある場合は、パスワード付きのフォルダにまとめておくと安心です。処分する情報は、データ消去ソフトを使って完全に削除し、復元されないようにすることも重要です。
ステップ3:パスワードとログイン情報の整理
デジタル終活において、最も重要かつ基本的なステップの一つが、パスワードとログイン情報の管理です。利用しているサービス名、ID、パスワードを一冊のノートにまとめる方法が推奨されています。
書き方については、1ページにつき1つのアカウント情報(サービス名、ID、パスワード)のみを記載し、情報が混在しないように次のページに進みましょう。
誰が見ても分かるように、文字は大きく、なるべくきれいに書くことが重要ですし、特に英数字や記号が混在するパスワードは、大文字・小文字の違いが明確に分かるように丁寧に記載しましょう。
修正方法として、書き間違えたり、パスワードを変更したりした場合は、修正液でしっかり消してから書き直すのが良いとされています。
二重線で消したり塗りつぶしたりすると、どれが正しい情報か分かりにくくなるためNGです。
なお、パスワードの使い回しは厳禁です。情報漏洩やハッキングがあった際に、芋づる式に危険が広がることを防ぎます。
ステップ4:エンディングノートへの記録と家族への共有
整理したデジタル資産情報は、エンディングノートに記録することが大切です。
エンディングノートには、スマートフォンのロック解除パスワードやパソコンのパスコード、利用しているサービスの名称やログイン情報、SNSのアカウント名、ネット銀行やネット証券の口座情報、そして残しておきたいデータや処分してほしいデータが入ったフォルダ名などを記載します。
エンディングノートは手書きでも構いませんが、インターネット上の無料テンプレートやエンディングノートアプリなどを活用することで、整然と読みやすいものを作成できるでしょう。
ノートが完成したら、その存在と保管場所を、自分と家族だけが知っている場所に保管し、家族にきちんと伝えておくことが非常に重要です。
隠してしまうと、いざという時に発見されないおそれがあります。また、このノートは絶対に家から持ち出さないようにしましょう。
ステップ5:定期的な見直しと更新
デジタル終活は一度行えば完了するものではありません。デジタルデータの内容は時間の経過とともに変化するため、定期的な見直しと更新が必要です。
見直しの目安として、年に1回、あるいは人生の節目や環境の変化に応じて見直しを行いましょう。
更新内容では、新たに使い始めたサービスがないか、残したいデータや処分してほしいデータが増えていないかなどをチェックし、解約・退会したサービスはリストから削除し、パスワードを変更した際には忘れずに最新情報に更新してください。
整理すべき主なデジタル資産の具体例
現代人が保有しているデジタル資産は多岐にわたります。デジタル終活の際には、以下のカテゴリの資産を洗い出し、整理することが特に重要です。
金融関連のデジタル資産
資産相続や遺産分割に直接関わるため、特に重要です。ネットバンキング口座では、ネット上での預金、定期預金、投資信託、外貨預金などを確認します。ネット証券口座では、株式、債券、投資信託、ETF、FXなどの取引データを把握しておきましょう。
仮想通貨取引所・ウォレットについては、ビットコイン、イーサリアムなど、秘密鍵の有無が生死を分ける重要な資産です。キャッシュレス決済アカウントでは、PayPay、楽天ペイ、LINE Pay、Apple Payなどに残る残高や履歴を確認します。
ポイント・マイレージの楽天ポイント、Tポイント、ANA・JALマイルなども実質的な資産になる場合があります。
契約・会員情報関連のデジタル資産
毎月の支払いが発生し続けている場合が多く、家族が把握していないと支払いトラブルになるリスクがあります。
サブスクリプション契約では、Netflix、Amazonプライム、Spotify、Hulu、DAZNなどの定額配信サービスを確認しましょう。
インターネットプロバイダー契約では、NTT、auひかり、ソフトバンク光などの契約情報を整理します。
スマートフォン・携帯電話の契約では、docomo、au、SoftBank、格安SIMなどの利用契約と料金引き落とし情報を把握しておくことが重要です。
各種有料会員登録では、オンライン学習サービス、趣味系の有料アプリ、オンラインサロンなども確認対象となります。
SNS・コミュニケーション関連のデジタル資産
故人の人生記録や思い出が集積される場でもあります。SNSアカウントでは、Facebook、Instagram、X(旧Twitter)、TikTokなどがあります。
追悼アカウントへの変更や削除申請の手続きを事前に確認しておくと良いでしょう。
チャット・メッセージアプリでは、LINE、WhatsApp、Messenger、Skypeなどのメッセージ履歴を整理します。
ブログ・動画配信アカウントでは、YouTube、note、個人ブログ、ニコニコ動画などの配信履歴・収益情報も忘れずに確認しましょう。
写真や動画、文書データなど思い出のデジタル資産
個人的な記録や思い出がデジタル上に大量に保存されています。
写真・動画データでは、家族写真、旅行動画、アルバムなどを整理します。文書・スキャンデータでは、契約書、保険証書、履歴書、年賀状データ、各種証明書などを確認しましょう。
電子書籍・電子コンテンツでは、Kindle、楽天Kobo、Audibleなどの購入済コンテンツも整理対象となります。
デジタル機器本体に保存されたデータ
クラウドサービスだけでなく、物理的に保管しているデジタル資産も忘れてはいけません。
パソコン・ノートPC内のデータ、スマートフォン・タブレット内のデータ、外付けHDD、USBメモリ、NASサーバーのほか、家庭用録画機、ゲーム機内データ、IoT家電設定情報なども確認対象です。
デジタル終活を行う際の注意点
デジタル終活は遺族の負担を減らす大切な準備ですが、整理の仕方によっては思わぬリスクやトラブルを生む場合もあります。
パスワードなどの重要な情報の適切な管理方法
ネット銀行のログイン情報など、財産に関する重要な情報は、自宅に金庫を用意するなど、人目につかないように保管し、情報漏洩を防ぐための工夫を行いましょう。
信頼できる人とのみ情報を共有し、誰に伝えたかを控えておくのが望ましいです。
ノートにパスワードを記載する際は「誰が見ても分かるように」丁寧に書くことが推奨されていますが、一方で「パスワードなどの重要な情報は見られないように保管する」「そのままエンディングノートに記録してしまうと情報漏洩リスクが高まる」という注意点も指摘されています。
悪用リスクを減らすために、パスワード自体を直接書かずに、「父の誕生日」や「過去に住んでいた住所の郵便番号」など、パスワードにつながるヒントを書いておくという方法も提案されています。
安全性を高めるためには、直接的なパスワードの記載は避け、信頼できるパスワード管理ツールと併用する、または、ヒントを記載しつつ、保管場所を厳重にするなどの工夫が必要です。
情報漏洩リスクへの対策とプライバシー保護
デジタル資産の中には、SNSやメッセージアプリのプライベートなやり取り、メールの内容、個人的な写真・動画、日記など、非常に個人的でセンシティブな情報が含まれます。
これらは第三者に開示すべきでない情報も多く、安易な情報共有はプライバシー侵害や家族間トラブルの火種になる恐れがあります。
不要な情報は生前に削除しておくこと、残したい情報は必要最小限に絞り、家族に残す情報と残さない情報を明確に分けること、整理したファイルにはパスワードをかけるなど、セキュリティ対策をしっかりと講じることが重要です。
法律・利用規約への配慮(デジタル遺言の法的効力など)
多くのオンラインサービスでは、「契約者本人のみが利用できる」と利用規約に明記されています。IDやパスワードを無断で使用すると、法律上は不正アクセスに問われる可能性もあるため注意が必要です。
各サービスの「死亡後の取り扱い」や「追悼アカウント」制度を事前に確認し、利用規約の範囲内で正規の手続きに則って対応することが求められます。
「遺言をデジタルデータで残せば良いのでは?」と考えがちですが、現行法では完全なデジタル遺言は法的効力を持ちません。
PDFやWord、クラウドに保存された遺言は裁判上遺言として認められないため、日本では紙の自筆証書遺言または公正証書遺言のみが有効です。
デジタル管理はあくまでエンディングノートや補助情報として利用し、正式な遺言は紙媒体で作成し、法務局や公証人役場で保管しましょう。
家族への適切な情報共有とトラブル回避
デジタル終活でエンディングノートを作成したとしても、家族がその存在に気付かなければ適切な対応ができません。
重要な情報が記載してあるからといって誰にも所在を知らせずに隠してしまうと、死後に発見されないおそれがあります。
デジタル終活をしたことや、具体的な内容、エンディングノートの保管場所を可能な範囲で家族に伝えておくと良いでしょう。
デジタル資産は形がなく価値が見えにくいため、相続時に家族間での認識の違いが起こりやすい分野です。
生前に家族で話し合い、自分の意向を説明しておくことで、無用なトラブルを避けることができます。
相続トラブルが懸念される場合は、弁護士など専門家への相談も検討しましょう。
また、ノートは絶対に家から持ち出さないでください。
まとめ
現代社会では、パソコンやスマートフォン、インターネットサービスの普及により、私たちの生活には膨大なデジタル資産が存在します。
これらを適切に整理し、家族が困らないよう準備するのが「デジタル終活」です。
デジタル終活は、個人の思い出と密接に関わるだけでなく、データが財産的価値を有する時代において、故人の名誉やプライバシーを害したり、財産を侵害してしまったりする危険を回避するためにも不可欠です。
「デジタル終活」は、端末さえあれば誰でも気軽に始められるものです。
自分自身と残された家族の負担を減らし、相続トラブルなどのリスクを未然に防ぐためにも、ぜひ本記事の内容を参考に、今日から早めに取り組むことをおすすめします。
一度で完結するものではないため、定期的な見直しと更新を習慣にすることで、安心して未来を迎えることができるでしょう。