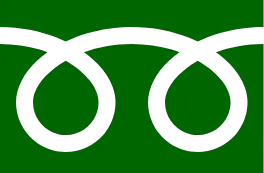近年、「生前整理」や「終活」といった言葉を耳にする機会が増えています。
これらの活動は人生の終わりに向けた準備として重要視されていますが、言葉が似ているため「具体的に何が違うのだろう?」「自分にはどちらが必要なのだろう?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、複数の情報源に基づき、生前整理と終活の目的や意味、具体的な違い、それぞれのメリット・デメリット、そして具体的な進め方について詳しく解説します。
この記事を読むことで、自分にとって最適な人生の準備の進め方が見えてくるはずです。

記事監修者プロフィール
遺品整理士歴10年、これまでに5,000件以上の遺品整理や特殊清掃に携わる。手がけた遺品整理で発見された貴重品のうち、お返ししたタンス預金の合計だけでも3億3千万円にも上り、貴金属などの有価物を含むと5億円近くの金品を依頼者の手元に返して来た。
遺品を無駄にしないリユースにも特化。東南アジアへの貿易を自社にて行なっており、それに共感を覚える遺族も非常に多い。また不動産の処分も一括で請け負い、いわるゆ「負動産」を甦らせる取り組みにも尽力して来た。
一般社団法人ALL JAPANTRADING 理事
一般社団法人家財整理相談窓口会員
一般社団法人除染作業管理協会理事
宅地建物取引士(日本都市住宅販売株式会社代表取締役)
株式会社RISE プロアシスト東日本
代表 仲井
生前整理とは?目的と必要性
生前整理の定義
生前整理とは、自分が生きている間に、身の回りのアイテムや財産を整理・処分することを指します。
単に物を減らすだけでなく、今後の自分の生活を見直し、より快適で充実した時間を過ごせるように、また、家族が円滑に過ごせる状況を作り出すための手法です。
自分が亡くなった後、家族が遺品整理に大変な思いをせずに済むように準備するという側面もありますが、それだけではありません。
死後を意識した活動であるとともに、残された人生をどのように生きるかを見つめなおすきっかけとなる、前向きな行動と捉えることができます。
生前整理が必要な理由・目的(メリット)
生前整理を行うことには、以下のような多くのメリットがあります。
| メリット | 詳細 |
| 自分自身の将来を良くするため | 老いとともに身体が不自由になる前に整理しておくことで、安全で快適な生活空間を確保できます。本当に大切なものだけに囲まれて生活できるようになり、より充実した人生を送ることにも繋がります。 |
| 家族の負担を軽減するため | 自分の死後、遺族が遺品整理や相続手続きに追われる負担を大幅に減らすことができます。何から手をつけていいか分からない、という状況を避けることができます。 |
| 不測の事態に備えるため | 事故や病気など、突然の困難に直面した際に、家族に伝えたいことや遺したいものを事前に用意しておくことができます。 |
| 相続トラブルを未然に防ぐため | 財産状況を明確にし、遺産の分配について自分の意向を事前に示しておくことで、家族間の無用なトラブルを防ぐ助けとなります。 |
| 自身の財産を把握するため | 整理を通じて、これまで把握できていなかった財産が見つかることもあります。これにより、今後の生活費の見直しや管理に役立ちます。 |
| 死への不安を解消するため | 人生の最期への準備を具体的に進めることで、漠然とした死への不安と向き合い、精神的な安定を得ることにも繋がります。 |
終活とは?目的
終活の定義
終活とは、人生の最後の段階に向けて、自分自身ができる限りの準備をすることを指します。
これは、単に死後の準備をするだけでなく、残りの人生をより豊かに、自分らしく生きるための活動全般を含みます。
つまり、生前整理は終活という大きな枠組みの中の具体的な活動の一つとして位置づけられます。
終活の目的
終活の主な目的は、以下の2つです。
- 残された家族に負担をかけないようにすること: 葬儀やお墓の希望、財産の相続などを事前に決めておくことで、遺族の精神的・物理的な負担を軽減します。
- 残りの人生を充実させること、悔いのない人生を送ること: 自分の人生を振り返り、本当にやりたいことを見つけ、それを実現するための活動も終活の一環です。より自分らしく余生を過ごすための「準備活動」と言えるでしょう。
終活の具体的な活動例
終活には、生前整理以外にも以下のような活動が含まれます。
- 遺言書の作成
- 葬儀やお墓の準備(場所、形式、費用など)
- エンディングノートの作成
- 医療や介護に関する希望の明確化(延命治療の意思表示など)
- 人間関係の整理(会いたい人に会う、感謝を伝えるなど)
- 今後の人生で本当にやりたいことを見つけ、それを実現するための活動(旅行、趣味、学習など)
- デジタル終活(スマートフォンやパソコン内のデータ整理、SNSアカウントの取り扱いなど)
生前整理と終活の主な違いを比較
生前整理と終活は密接に関連していますが、いくつかの点で違いがあります。
| 比較ポイント | 生前整理 | 終活 |
| 関係性 | 終活という大きな枠組みの中の具体的な活動の一つ。主に「物」や「財産」の整理が中心。 | 生前整理を含めた、人生の最期を迎えるための活動全般。 |
| 主な目的 | 死後の遺族の負担軽減、自身の今後の生活の見直し、快適な生活空間の確保。 | 残りの人生をより良く生きるための活動全般、人生の充実、家族への配慮。 |
| 始める時期 | 明確な決まりはないが、一般的には60歳頃が目安とされることが多い。体力的な負担も考慮される。 | 人それぞれで、20代や30代の若い頃から意識し始める人も多い。思い立った時が始め時。 |
| イメージ | 「亡くなることを覚悟して生きる」という、やや重みのあるイメージを持つ人もいるかもしれない。 | 「亡くなるまでにやりたいことをイメージする」「残りの人生をどう楽しむか」という、比較的明るく前向きなイメージ。 |
| 老前整理との違い | 「自分の死後(老後)」や「家族のため」という意味合いが強い。 | 老前整理も終活の一つ。老前整理は特に「自分の老後のため」の快適な生活準備という意味合いが強い。 |
生前整理を始める最適なタイミングは?
生前整理を「何歳から始めなければならない」という明確な決まりはありません。
しかし、一般的には60歳が目安とされることが多いようです。これは、定年退職によって時間的な余裕ができたり、健康状態に変化を感じ始めたりする時期と重なるためです。
しかし、若い頃から始めることにもメリットがあります。体力があるうちに無理なく進められますし、突然の病気や事故といった不測の事態にも備えることができます。
実際には、以下のような人生の節目が生前整理を始めるきっかけとなることが多いようです。
- 結婚
- 引越し
- 転職
- 定年退職
- 子どもの独立(育児卒業)
- 親の介護卒業
- 家のリフォーム前
- 高齢者施設への入居前
大切なのは、ご自身の健康状態、仕事の状況、家族構成などを考慮し、「そろそろ考えようかな」と思ったタイミングで、無理なく取り組むことです。


生前整理で具体的にやるべきこと
生前整理は、具体的にどのようなことから始めれば良いのでしょうか。主なステップとポイントをご紹介します。
STEP①:必要なものと不要なものを分ける(物の整理・断捨離)
まずは、身の回りの「物」の整理から始めましょう。
- 判断基準: 自分にとって本当に必要か、今後も使う可能性があるか。また、家族にとっても必要かどうかを考えましょう。
| コツ | 詳細 |
| コツ1:思い入れが少ないものから始める | 書類や衣類など、比較的判断しやすいものから手をつけるとスムーズです。 |
| コツ2:一度にすべてを終わらせようとしない | 「今日はこの引き出しだけ」「今週はクローゼット」というように、計画的に少しずつ進めるのが長続きの秘訣です。 |
| コツ3:遺された人の目線で整理する | 自分にとっては大切でも、他の人にとっては価値が分からないものもあります。 |
| 不用品の処分 | 自治体のルールに従って処分するほか、リサイクルショップやフリマアプリ、不用品回収業者などを利用する方法もあります。 |
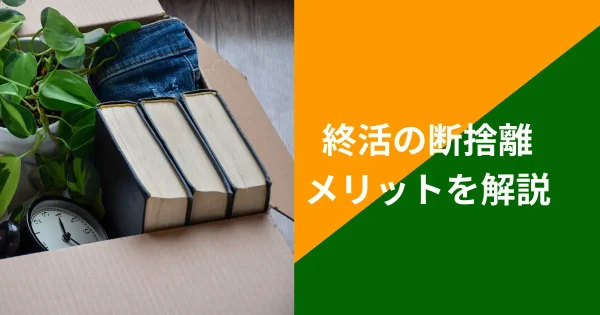
STEP②:財産を整理する(財産目録の作成)
次に、お金に関わる「財産」を整理します。
- 対象: 不動産(土地、建物)、預貯金、有価証券(株、投資信託など)、生命保険、貴金属、骨董品、借金(ローンなど)、プラスマイナス問わず全ての財産情報をまとめます。
- 財産目録の作成: どこに何がどれくらいあるのかを一覧表(財産目録)にすることで、現状を正確に把握できます。これは、相続時の手続きをスムーズに進めるためにも非常に重要です。
- 重要性: お金に関するトラブルを未然に防ぐためにも、財産の整理は不可欠です。
STEP③:貴重品をまとめる
通帳、印鑑、権利書、保険証券、パスポート、マイナンバーカード、年金手帳など、重要な書類や貴重品は一箇所にまとめて保管しましょう。
- 目的: 万が一の際に迅速に対応でき、遺族が探し回る負担を軽減できます。
- 保管場所: 家族にも分かりやすい場所に保管するか、保管場所を伝えておきましょう。貸金庫を利用するのも一つの方法です。
STEP④:遺言書を作成する
自分の死後、財産を誰にどのように分配したいかなど、最終的な意思を伝えるための重要な文書が遺言書です。
- 法的効力: 遺言書には法的な効力があり、一定のルールに則って作成する必要があります。
- 種類: 主に「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があります。
- 専門家への相談: 法的効力を持たせるためには専門知識が必要な場合もあります。特に財産が多い場合や複雑な相続関係の場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談し、公正証書遺言を作成することが推奨されます。

情報の整理(デジタル終活を含む)
物や財産だけでなく、「情報」の整理も重要です。
- アナログ情報: 印鑑や通帳の保管場所、銀行口座情報(金融機関名、支店名、口座番号)、加入している保険の内容などを整理し、一覧にしておきましょう。
- デジタル情報(デジタル終活):
- パソコンやスマートフォン内のデータ(写真、動画、メール、連絡先など)を整理します。不要なものは削除し、残したいものはバックアップを取っておきましょう。
- オンラインアカウント(SNS、ネットバンキング、ショッピングサイトなど)のIDやパスワードを一覧化し、信頼できる家族にだけ分かるように保管します。
- 遺族に見られたくないアカウントは、事前に削除するなどの対応も検討しましょう。

エンディングノートの作成
エンディングノートは、自分の基本的な情報や、死後家族に伝えたいこと、葬儀やお墓の希望、医療・介護に関する自分の意思、家族へのメッセージなどを自由に記録しておくノートです。
遺言書のような法的効力はありませんが、葬儀やお墓の希望、延命治療の意思、ペットの世話について、大切な人へのメッセージなど、形式にとらわれず自由に記載できます。
財産やデジタルデータの一覧としても活用でき、遺族が故人の意思を把握し、様々な手続きを円滑に進めるのに役立ちます。
また、自分の想いを整理する良い機会にもなります。市販のエンディングノートには、あらかじめ項目が用意されているものが多く、書き忘れを防ぐのに便利です。遺言書とエンディングノートは目的が異なるため、法的な拘束力が必要な財産分与などは遺言書に、それ以外の希望やメッセージはエンディングノートに、と両方作成することが推奨されます。
形見分けのことも考えておく
大切にしていた品物を、誰に受け取ってほしいかを事前に考えておくことも、生前整理の一つです。
- 目的: 遺品を巡る家族間のトラブルを防ぎ、自分の思い出や価値を大切な人に継承することができます。
- 方法: エンディングノートに記載したり、直接本人に伝えたりする方法があります。
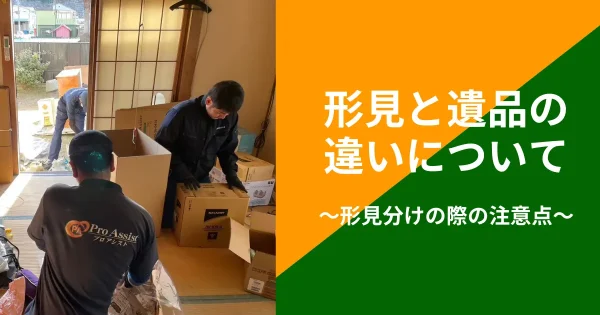
大事な書類は捨てないように確認する
物を処分する際には、財産に関する文書(契約書、権利書など)、保険関連の書類、年金手帳など、重要な書類を誤って捨ててしまわないよう、一つひとつ丁寧に確認しましょう。
判断に迷う場合は、一時的に保管箱などに入れておき、後日改めて確認するか、専門家に相談するのも良いでしょう。
生前整理のデメリットと対策
生前整理には多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも考えられます。事前に対策を練っておきましょう。
| デメリット | 対策 |
| 時間や労力がかかる | 時間に余裕のあるタイミング(定年後、子どもの独立後など)で、少しずつ計画的に取り組む。 |
| 不用品の処分に費用がかかる場合がある | 処分する時期を分けたり、買取サービスを利用したりして費用を抑える工夫をする。自治体の粗大ごみ処理手数料なども事前に調べておく。 |
| 自分一人ではできない可能性がある(大型家具など) | 家族や友人に手伝ってもらう。無理せず、できる範囲で行う。 |
| 思い出の品などで感傷的になり、途中で挫折してしまうことがある | 無理に一度に処分しようとせず、一時保管する場所を設けるなど、気持ちの整理をしながら進める。家族と思い出を語り合いながら整理するのも良い方法。 |
生前整理を効率的に進めるコツ
生前整理は、時に大変な作業になることもあります。効率的に進めるためのコツをご紹介します。
家族と一緒に進める
一人で抱え込まず、家族と協力することで、生前整理は格段に効率的に進められます。
- 物の要不要の判断に迷った際に、客観的な意見をもらえます。
- 大きな物の移動や処分がスムーズになります。
- 家族の思い出の品について話し合う良い機会になります。
- 家族が生前整理の重要性を理解し、協力的になるきっかけにもなります。
専門業者に相談する
自分たちだけでは難しい場合や、より専門的なアドバイスが欲しい場合は、生前整理や終活の専門業者に相談することも有効な手段です。
- 整理のプロセスや財産管理、複雑な法的手続きに関する専門知識やサポートが受けられます。
- 不用品の分別、搬出、適切な処分までを専門的に行ってくれます。
- 物の仕分けや処分方法で悩んでいる場合に、具体的なアドバイスをもらえます。
- 体力的な負担や精神的なストレスを軽減できます。
複数の業者から見積もりを取り、サービス内容や料金を比較検討しましょう。無料で見積もりや相談を行っている業者もあります。口コミや実績なども参考にすると良いでしょう。
まとめ
生前整理と終活は、どちらも人生の終わりに向けた大切な活動であり、生前整理は終活という大きな枠組みの中の一つと理解することができます。
主な違いは目的にあり、生前整理は主に「死後」の遺族の負担軽減や自身の今後の生活環境の改善を目的とするのに対し、終活は「残りの人生」そのものをより充実させ、自分らしく生きるための活動全般を指します。
どちらの活動も、始めるのに「遅すぎる」ということはありません。ご自身の体力や状況に合わせて、できるだけ早めに、元気なうちから少しずつ始めることが推奨されます。具体的な活動としては、物の整理、財産整理、遺言書やエンディングノートの作成、デジタル終活など、多岐にわたります。
時間や労力がかかる場合や、一人で進めるのが難しいと感じる場合は、無理をせず家族と協力したり、専門業者に相談したりすることも有効な選択肢です。
計画的に生前整理や終活を進めることで、今後の人生をより安心して過ごし、大切な家族への負担を減らすことができます。この記事が、皆様にとってより良い人生の準備を進めるための一助となれば幸いです。