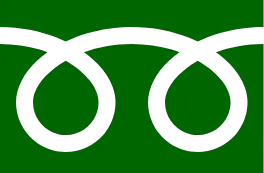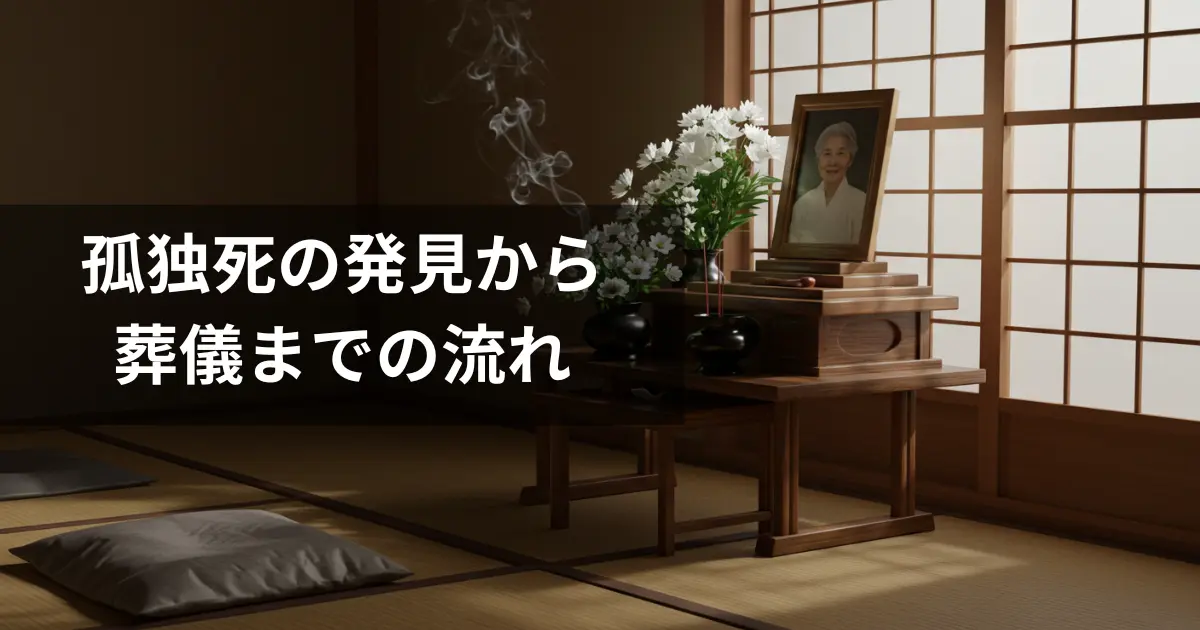近年、単身世帯の増加や高齢化に伴い、「孤独死」は誰にとっても他人事ではない社会問題となっています。
もしも孤独死の現場に遭遇してしまったら、あるいは身内が孤独死してしまったら、一体何から手をつければ良いのでしょうか。
葬儀はどのように進むのか、費用は誰が負担するのか、身寄りがいない場合はどうなるのか、そして特殊な清掃が必要になるケースも…。
この記事では、そのような孤独死にまつわる様々な疑問や不安を解消するため、孤独死が発見された際の初動対応から葬儀の流れ、費用、身寄りのない場合の対応、さらには特殊清掃の必要性や孤独死を避けるための対策を解説します。
この記事を読むことで、万が一の事態に直面した際に、落ち着いて適切な対応ができるようになることを目指します。

記事監修者プロフィール
遺品整理士歴10年、これまでに5,000件以上の遺品整理や特殊清掃に携わる。手がけた遺品整理で発見された貴重品のうち、お返ししたタンス預金の合計だけでも3億3千万円にも上り、貴金属などの有価物を含むと5億円近くの金品を依頼者の手元に返して来た。
遺品を無駄にしないリユースにも特化。東南アジアへの貿易を自社にて行なっており、それに共感を覚える遺族も非常に多い。また不動産の処分も一括で請け負い、いわるゆ「負動産」を甦らせる取り組みにも尽力して来た。
一般社団法人ALL JAPANTRADING 理事
一般社団法人家財整理相談窓口会員
一般社団法人除染作業管理協会理事
宅地建物取引士(日本都市住宅販売株式会社代表取締役)
株式会社RISE プロアシスト東日本
代表 仲井
孤独死とは?
孤独死の定義
孤独死とは、一般的に「誰にも看取られることなく、自宅などで生活していた人が死亡すること」を指します。
特に、死後しばらく経ってから発見されるケースが多く、社会からの孤立が背景にある場合が少なくありません。
孤独死と孤立死の違い
類似した言葉に「孤立死」がありますが、孤独死が「一人で亡くなる」という状況を指すのに対し、孤立死は「社会的に孤立した状態で亡くなる」という、より社会的な背景を含んだニュアンスで使われることがあります。
しかし、明確な定義が法律などで定められているわけではなく、この記事では一般的に認識されている「孤独死」として解説を進めます。
孤独死が増加している背景
核家族化の進行、地域社会との繋がりの希薄化、そして高齢者人口の増加などを背景に、孤独死は年々増加傾向にあると言われています。
これは、決して特別なことではなく、誰の身にも起こりうる問題として認識する必要があります。
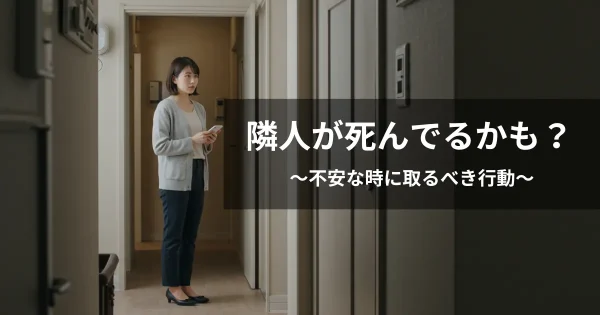
孤独死の発見時の対応
孤独死は、郵便物が溜まっている、異臭がする、長期間連絡が取れないといった状況から発見されることが一般的です。
万が一、孤独死の現場に遭遇してしまった場合、パニックにならず冷静に対応することが重要です。
生死の判断がつかない場合は救急車(119番)
まず、ご遺体がまだ息がある可能性がある、または生死の判断がご自身ではつかない場合は、ためらわずに救急車(119番)を呼んでください。
救急隊員が到着するまでは、ご遺体にむやみに触れたり、室内の物を動かしたりしないようにしましょう。
明らかに死亡している場合は警察(110番)
明らかに亡くなっていると判断できる場合(腐敗が進んでいるなど)は、警察(110番)に連絡します。警察が到着し、現場検証や検視を行うことになります。
現場保存を徹底すること
いずれの場合も、警察や救急隊が到着するまでは、ご遺体や現場のものには絶対に触れないでください。
事件性の有無を判断するため、現場の状況を保全することが非常に重要です。窓を開けて換気することも控えましょう。
孤独死発見から葬儀までの流れ(遺族がいる場合)
孤独死の場合、一般的な死亡とは異なり、警察の介入が必須となるため、葬儀までの流れも通常とは異なります。
警察による現場検証と検視
警察が到着すると、まず事件性の有無を調べるために現場検証と検視が行われます。
この間、遺族や関係者であっても現場への立ち入りは制限されます。身元を確認するための情報収集や、死因を特定するための調査が行われ、室内の金品などが一時的に警察によって保管されることもあります。
警察から遺族への連絡と遺体の引き渡し
故人の身元が判明次第、警察から血縁関係の近い順に連絡が入ります。
ただし、身元がすぐに特定できない場合や、ご遺体の腐敗が進んでいる場合は、身元判明までに時間がかかることがあります。
事件性がないと判断され、死因が特定されると、警察からご遺体と、一時的に保管されていた貴重品などが遺族に引き渡されます。
この際、「死体検案書(または死亡診断書)」が発行されるので、これをもって死亡届を7日以内に役所へ提出する必要があります。
ご遺体は、警察署内の霊安室や民間の安置施設に一時的に保管されることになりますが、保管費用が発生する場合があることも念頭に置いておきましょう。

葬儀の準備と実施
ご遺体の引き渡しには数日から数週間かかる場合があるため、その期間を利用して葬儀の準備を進めることが大切です。孤独死の場合、ご遺体の状態によっては衛生面を考慮し、火葬を優先する「直葬(火葬式)」が選ばれることが一般的です。
また、ご遺体の腐敗が進んでいる、あるいは長距離の搬送が困難であるといった理由から、発見場所の近く(故人の住民登録地など)で火葬を行うケースが多く見られます。これは、住民登録地であれば火葬費用が安くなる場合があるというメリットも考慮されてのことです。
葬儀を行う場合は、一般的な葬儀の流れに沿って進められますが、まずは葬儀社に連絡し、孤独死のケースであることを伝えて相談しましょう。孤独死の葬儀に対応しているか、特殊な状況への理解があるかなどを事前に確認することが重要です。
身寄りがない場合・遺族が引き取りを拒否した場合の対応
身寄りが全くいない方や、様々な事情から遺族がご遺体の引き取りを拒否する場合もあります。そのような場合でも、ご遺体が放置されることはありません。
自治体による火葬と埋葬
「行旅病人及行旅死亡人取扱法」という法律に基づき、引き取り手のないご遺体は、故人が住民登録をしていた自治体(市区町村)が火葬および埋葬を行います。この場合、原則として葬儀(通夜や告別式など)は行われず、火葬のみが執り行われます。
火葬後のご遺骨や、故人の遺品は、自治体によって一定期間保管されます。保管期間は自治体によって異なりますが、一般的には5年程度とされることが多いようです。この期間内に引き取り手が見つからなければ、無縁塚(共同墓地)に合祀されることになります。一度合祀されると、後から個別にご遺骨を取り出すことはできません。
近隣住民や友人が葬儀を手配するケース
法律上の遺族がいなくても、故人と親しかった友人や知人、あるいは賃貸物件の大家さんなどが、費用を負担して葬儀を手配するケースもあります。
孤独死の葬儀費用について
孤独死の場合の葬儀費用は、誰が負担するのでしょうか。
また、経済的に困難な場合に利用できる制度はあるのでしょうか。
費用負担の原則
まず原則として、故人に遺産がある場合は、その遺産から葬儀費用が支払われます。
遺産がない、または不足する場合は、葬儀を行った親族(喪主)が負担することになります。
活用できる補助金制度
経済的な事情で葬儀費用を支払うことが困難な場合、以下のような補助金制度を利用できる可能性があります。
葬祭扶助制度
生活保護を受給していた故人や、葬儀を行う遺族(扶養義務者)が生活保護を受給しているなど、経済的に困窮している場合に利用できる制度です。
この制度は、遺族だけでなく、大家さんや友人など、遺族以外の方が故人のために葬儀を手配した場合にも適用されることがあります。
支給されるのは、あくまで火葬を中心とした最低限の葬儀(直葬)にかかる費用であり、一般的な葬儀費用全額が賄えるわけではありません。
支給額の目安は自治体によって異なりますが、20万円前後が一般的です。故人に遺産がある場合は、その金額が差し引かれて支給されます。
重要な注意点として、葬祭扶助制度を利用する場合は、必ず葬儀を行う前に自治体の福祉事務所などに申請する必要があります。 葬儀後に申請しても認められないため、注意が必要です。
その他の制度
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合は「葬祭費」、社会保険(健康保険組合など)に加入していた場合は「埋葬料」または「埋葬費」といった形で、数万円程度の給付金が支給される場合があります。
これらも申請が必要ですので、該当する窓口に確認してみましょう。
補助金制度の概要
| 制度名 | 対象者 | 内容 | 支給額の目安(自治体により異なる) | 申請タイミング・注意点 |
| 葬祭扶助制度 | 生活保護受給者の故人、または葬儀を行う遺族(扶養義務者)が生活保護受給者など経済的に困窮している場合。大家や友人なども対象になることがある。 | 火葬を中心とした最低限の葬儀(直葬)費用 | 20万円前後(故人に遺産がある場合は差し引かれる) | 葬儀を行う前に自治体の福祉事務所などに申請。葬儀後の申請は不可。 |
| 葬祭費 | 故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合 | 葬儀費用の一部 | 数万円程度 | 該当する窓口に確認・申請が必要 |
| 埋葬料・埋葬費 | 故人が社会保険(健康保険組合など)に加入していた場合 | 埋葬費用の一部 | 数万円程度 | 該当する窓口に確認・申請が必要 |
葬儀以外に必要な手続きと対応
孤独死の場合、葬儀を終えた後にも、様々な手続きや対応が必要になります。
各種契約の解約手続き
故人が契約していた電気、ガス、水道などの公共料金、電話やインターネット回線、クレジットカード、保険、年金、そして賃貸物件の契約解除など、多岐にわたる解約手続きが必要です。
遺品整理
故人が残した遺品の整理も重要な作業です。
しかし、孤独死の現場は、ご遺体が発見されるまでの期間や状況によって、通常の遺品整理とは異なる困難さが伴う場合があります。
体液や汚物、害虫などが発生していることもあり、個人での作業が精神的にも肉体的にも大きな負担となることがあります。
このような場合は、無理をせず、遺品整理を専門に行う業者に依頼することも検討しましょう。

孤独死現場の特殊清掃
孤独死の現場、特に発見までに時間が経過したお部屋は、通常のハウスクリーニングでは対応できないほど汚染されているケースが少なくありません。
血液や体液の付着、腐敗による強烈な臭い、害虫の発生など、専門的な知識と技術を持った「特殊清掃業者」による原状回復作業が必要となります。
これは、次の入居者のためだけでなく、近隣住民への配慮や、賃貸物件の価値を維持するためにも非常に重要です。
孤独死現場の特殊清掃とは?
「特殊清掃」という言葉を初めて聞く方もいらっしゃるかもしれません。これは、孤独死や事件・事故現場など、通常の清掃では対応できない特殊な状況下で行われる専門的な清掃作業のことです。
特殊清掃の具体的な内容
特殊清掃業者は、以下のような専門的な作業を行います。
- 汚物・体液の除去・清掃:血液、体液、汚物などを適切に除去し、清掃します。
- 除菌・消毒:感染症のリスクをなくすため、専用の薬剤を用いて徹底的に除菌・消毒します。
- 消臭作業:孤独死現場特有の強烈な死臭や腐敗臭を、オゾン脱臭機などの専門機材や薬剤を用いて除去します。この消臭作業が最も技術を要する部分の一つです。
- 害虫駆除:発生した害虫(ウジやハエなど)を駆除し、再発を防ぎます。
- 遺品整理:必要に応じて、汚染された遺品の仕分けや処分も行います。
なぜ通常の清掃では不十分なのか
孤独死の現場は、目に見える汚れだけでなく、壁や床の内部にまで体液が浸透していたり、強烈な臭いが染み付いていたりすることがあります。
特に臭いは、表面的な清掃だけでは除去できず、専門的な知識と技術、専用の機材がなければ完全に取り除くことは非常に困難です。
中途半端な清掃では、後から臭いが再発したり、害虫が発生したりする可能性があります。

早めに特殊清掃業者に依頼すべき理由
孤独死の現場を発見したら、できるだけ早く特殊清掃業者に相談・依頼することが重要です。
時間が経つほど汚染は拡大し、臭いも強くなり、原状回復が難しくなる可能性があります。
また、近隣への臭いの影響や、賃貸物件の場合は家賃が発生し続けるといった問題も考慮する必要があります。
特殊清掃業者の選び方のポイント
信頼できる特殊清掃業者を選ぶためには、以下のポイントを確認しましょう。
- 実績と経験:孤独死現場の清掃実績が豊富か。
- 専門知識と技術:特に消臭技術に自信を持っているか。
- 見積もりの明確さ:作業内容と費用が明確に提示されるか。追加料金の発生条件なども確認しましょう。
- 対応の迅速さ・丁寧さ:問い合わせへの対応が迅速で、親身に相談に乗ってくれるか。
- 許認可:産業廃棄物収集運搬業許可など、必要な許認可を得ているか。
- 守秘義務の遵守:プライバシーへの配慮があるか。
いくつかの業者に見積もりを依頼し、比較検討することをおすすめします。

まとめ
孤独死は、発見時の対応から葬儀、その後の手続きに至るまで、通常のお別れとは異なる多くの対応が求められます。
この記事では、その流れや費用、身寄りがない場合の対応、そして非常に重要な特殊清掃の必要性について解説してきました。
万が一、孤独死という現実に直面した際には、パニックにならず、まずは警察に連絡し、指示を仰ぐことが大切です。
そして、葬儀やその後の手続きについては、葬儀社や特殊清掃業者といった専門家の力を借りながら、一つ一つ進めていくことが重要です。
この記事が、孤独死に関する不安を抱える方々にとって、少しでもお役に立ち、いざという時に適切な行動をとるための一助となれば幸いです。